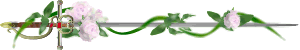
|
■シャルルマーニュ伝説 |
サイトTOP>2号館TOP>コンテンツTOP | |
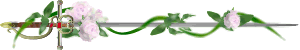
場面は、シャルル王がイスパニア(スペインのこと)攻略のため7年を費やし、国中のほとんどの場所を制圧し終わったところから始まる。(ここからして、実際のイスパニヤ攻略の歴史的事実からは遠いが、脚色として流しておこう。)
スペイン王・マルシルは、山間いの砦、サラゴッズに追い詰められていた。
マルシルのもとには二万以上の兵があったが、それでもシャルルマーニュ側には勝てない。もはや打つ手なしとなった王は、智将・ブランカンドランを召し、いかがせりと問う。
ブランカンドランは答えて言う、「シャルルマーニュのもとに使者を遣わし、忠誠を誓うと伝えさせなされ。贈り物をして喜ばせなされ。キリストの教えに帰依する、サン・ミシェルの祭りに出席すると伝えなされ。その証として人質を送るのです、10人でも、20人でも、信用されるまで。私も息子を送りましょう。その子らみな、殺されようとも」
ブランカンドランは最初から、シャルルマーニュに屈服する選択肢を持っていない。この提案は、フランスの軍勢に引き上げてもらうための偽りである。実際にサン・ミシェルのお祭りになったとき、マルシルはシャルルマーニュのもとに現れない。約束を破られたと知った王は怒って人質たちを殺すだろう。だが、「このままイスパニアの国を奪われるよりは、はるかにまし」だと、ブランカンドランは言う。
これを聞き、マルシルは「そのように」と答え、さっそく使者をたてるのだった。
さて、使者の答えを聞くべく待ち受けるフランス王シャルル、歴史上の年齢と違って、白髪、白髭の堂々たる老人の姿をしている。周りには、ロラン、オリヴィエを含む12人衆。ルネッサンス版の12人衆とはかなりメンツが違っている。(この”12人”という人数は、ディートリッヒ伝説でもベーオウルフでも登場する。日本でいう四天王のような、いわばお約束の数字だ)
マルシル王の使者・ブランカンドランからの申し出を聞いても、シャルルは半信半疑。なぜなら、過去にも同じように恭順の誓いをした時に、フランス側からの使者、バザンとバジールを斬り捨てたからである。シャルルは今回も偽の和睦だと疑っていた。だが、ガヌロン伯は言う、「申し出を無下に退けるのはいかがなものか」。また重臣ネームも進み出て言う、「ガヌロン殿の言うことも最もです、戦いに敗れたマルシルをこれ以上攻めるのはいささか罪なるかと」
そこで人々は、「なるほど、そうかもしれぬ」と納得した。
「さて、では一体誰が使者として発つべきか。」シャルルマーニュが人々に問う。だがシャルルも、サラセン人が本気で恭順の誓いをするのかどうか、まだ半信半疑である。相談役のネームをはじめ、血気盛んなロランなど、重臣たちには行くなと命ずる。
そこへロランが提案する。「わが義父、ガヌロンをば行かせ給え。」人々みな納得し、「そうだ、ガヌロンがよい。大いなる知恵者ガヌロンこそ相応しい。」だが、これを聞いたガヌロンは苦悶に顔をゆがめ、きっとロランをにらみ付けた。「おのれロラン。よくもわしを指名したな。よくも義父を危険な任務につかせおるわ!」…どうやらガヌロンはかなり行きたくないらしい。
「ならば私が行きましょうか?」「たわけめ、指名されたからには退けぬわ。わしが生きて戻った暁には、手痛い目にあわせてくれようぞ。」そんな脅しにもロランは笑っているだけである。
ガヌロン伯は主君シャルルに向かって言う。「参らねばならぬというならサラゴッズへ参りましょう。ただ、わしはもう生きて帰れぬものと思いまする。わしが戻らぬときには、一人息子ボードワンに目をかけてくださるよう。わが息子にはすべてを譲る所存にございます。」
シャルルマーニュは苦笑する。「そう気が弱くてはのう。」(当然の反応だ)
王は使者の証たる、手袋と御杖を差し出した。受け取ろうとしたガヌロンだが、ふとした弾みに受け取り損ね、和平のしるしである手袋がはたと地面に落ちる。フランス人は不吉な予感を感じ取るが、ガヌロンは素早く場を発ち、自らの陣屋へ帰ってしまった。ガヌロンの叔父ギルメールも、義理とはいえ、親しい親子の間柄で危険な任務に指名したロランに恨み節。
こうして、やる気のゼロに等しい(と、いうか別な方向にヤル気を見せている)不吉な使者が差し向けられた時、悲劇は始まった。
さて、サラセン人のもとへたどり着き、ブランカンドランと出合ったガヌロン伯。まずブランカンドランはシャルルマーニュの偉業を褒めたたえ、イスパニヤに何を望むのか、と、さぐりを入れる。ガヌロンはそれは分からぬと答えつつも、シャルルマーニュをけしかけているのは彼の甥ロランだ、その思い上がりぶりは甚だしいものと囁く。
ブランカンドランも同調して言う、「にっくきはロラン、世界のすべての国々を屈服させ、支配しようとでもいうのか。」
ガヌロン「全くだ。フランスをして、世界の覇者と成すつもりか。」
ブランカンドラン「…気があうのう、おぬしとは」
ガヌロン「うむ。」
ロラン嫌いで意気投合。かくてブランカンドランはマルシルの御前にガヌロンを紹介するとき、好意を持って成した。ガヌロンはわざとに弁舌爽やかに用向きを告げる、すなわち、キリストの教えに服し、シャルルマーニュの家臣としてイスパニアの領主となるがよい、と。もしこれを受け入れなくば命は無い。
マルシルは怒りに震え、ガヌロンを斬捨てようとするも、部下に止められる。
ガヌロンはさらに言う、「シャルル王の仰せには、そこもとはキリストの教えに服せよとのこと。さすれば、イスパニアの国の半分は、そこもとの手に残される。しかるに残る半分は、甥なるロランに与えるとのこと。さ、お受け取りくだされ。これが王の親書なれば」
親書には、マルシルの忠臣であるアルガリフを人質として寄越すように、と書いてある。最初から裏切るつもりの取引なれば、応じればアルガリフの命は無い。これにはマルシルも、その息子ジュルファレも怒りで顔色を失うが、あわやガヌロンを斬捨てんというとき、ブランカンドランが進み出て、「お待ちくだされ、かのフランス人はお役に立ちますゆえに」と、進言する。
それを聞いてマルシルは考えを変えた。ガヌロンに高価な贈り物をして機嫌をとりつつ、いかにすれば、被害をおわずシャルルマーニュに撤退してもらえるものかと相談を持ちかける。
ガヌロン「王は戦をお止めにはならぬでしょう。その甥、ロランの命あるうちは。その友なるオリヴィエもまた、手ごわい。シャルルの周り固める13人衆が、フランスの二万の軍勢を率いておりまする」
右腕たるロランと、その親友オリヴィエある限り、シャルルマーニュは戦意を失うまい、つまりロランとオリヴィエを殺せ、というのである。
「無駄な血を流す策はおやめなされ。此度は人質を20人も送れば、シャルル王も納得して国へ戻るでしょう。しんがりには、必ずロランとオリヴィエの軍が残りまする。この2人さえ討ち取れば、もはやフランスが二度と侵攻して来ることは、ありますまい。」
これを聞いてマルシルは喜び、ガヌロンに親愛の口付けをする。
「しかし、何ら誓約の無いのでは心許ない。そなたには、ロラン謀滅を企てる用意はおありか」
「無論のこと。」と、ガヌロンは剣に誓いをたてる。かくて企みは成り、ガヌロンには高価な贈り物が成される。使者は友好の意を持ち帰るが、その裏で、シャルルマーニュの引き上げるとき、マルシルは軍を率いてしんがりをつとめるロランとオリヴィエを討つ算段となっていたのである。
裏切り者ガヌロンはガルヌの町へと帰り着く。待ち受けるシャルルと廷臣たちの前に、マルシルより託されたサラゴッズの城門の鍵を差し出し、マルシルは親書にあった申し出を受けるつもりでいる、と述べる。
しかして、20人の人質を差し出すことについては逆らわぬが、アルガリフをその中に交えよとの命だけは赦免して欲しいとの旨、告げる。
これを聞いてシャルルマーニュは、マルシルが軍門に下ることを承知したものと考え、ガヌロンの労をねぎらい、戦は終わったと皆に引き上げを告げる。イスパニヤ攻略はこれで終わった、みなフランスへ戻るのだ、と。人々は、恐るべき裏切りをまだ知らぬ。
その夜、眠るシャルルマーニュは、シジェール渓谷にいる夢を見た。
両の手に持っていたトネリコの枝をガヌロンが奪い、凄まじく振り回し、地面に叩きつけて折ってしまうという夢だった。不吉な夢は、未来を予言する。その頃、サラセン人の軍勢40万、鎧兜を身に纏い、ロランの軍を討つべく、山間(やまあい)に身を潜ませていたのだった。
やがて夜が明けた。
いざ出立というとき、シャルルマーニュは問う。「さて、誰が殿軍(しんがり)を務めるべきか」と。敵に背を向けて撤退するのだから、最後をつとめる者は危険にさらされる。まして、相手は、恭順の誓いをしたとはいえ、過去に裏切ったことのあるマルシルである。
無論、最後をつとめるものはロランとオリヴィエでなくてはならない。ここでガヌロン言う、「わが継子ロランこそ。あれほど武勇のある者はおりますまい。」 「しかして先頭はいかがする」 「デンマルクのオジエ殿。かの方を除いて、他にはありますまい。」
ガヌロンは、危険な使者をつとめさせられたお返しに、危険なしんがりの役をロランに押し付けたことになる。
自分がしんがりに指名されたことを知るロランは怒り心頭、義父を非難しつつ、この役目は必ず果たすと誓う。ガヌロンは使者の証たる手袋を取り落としたが自分はそのような失態はせぬと言い、指揮官の証たる弓をシャルルマーニュの手より受け取る。
かくて、待ち受ける伏兵40万、ロラン率いるフランスの軍勢2万。ガヌロンのはかりごとにより、ロンスヴァルの谷間において、血戦の幕は上がるのであった。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()