騎士といえば「一騎打ち」。騎士叙事詩において、主人公と敵との「一騎打ち」シーンは、一番の盛り上がり場所だ。騎士は戦う職業、それゆえ騎士たちは決闘を避けて通れず、一国の王と名乗る騎士たちさえ、一騎打ちを挑まれれば、己の力だけで相手に勝たねばならなかった。命と名誉、そして時には愛すらも賭けて、正々堂々と戦う「一騎打ち」は、いわば騎士だけに許された華々しい儀式だったのだ、
騎士の決闘には、スポーツと同じく様々な「ルール」があり、それに則って戦うことが重要とされた。”どんな方法でもいいから勝てばいい”というものではなく、ルール違反をして勝っても、不名誉にしかならなかったのである。
その「一騎打ち」の、大雑把なルールを紹介しよう。
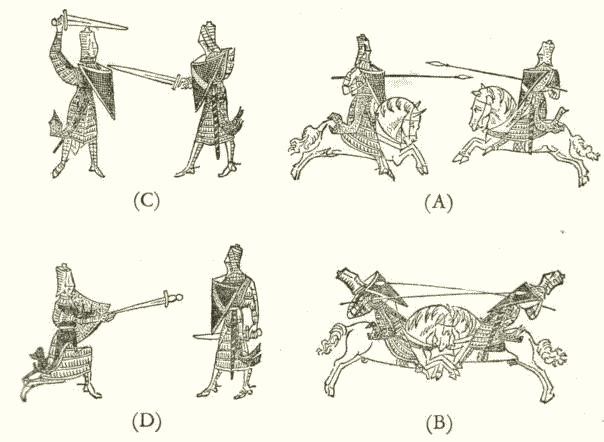
※図資料/「パルチヴァール」(郁文堂)より
決闘のはじまりの合図は普通、騎士のお付きの小姓が出していた。
小姓といっても召使ではなく、来立派な騎士になるべく一人前の騎士のもとで勉強している騎士の子弟。主に取り立ててもらえば剣持つ身になれる人たちで、いわば予備戦力である。強い、良い主に仕えた小姓は、主から戦利品の一部を譲り受けることもあったが、主が負けた場合、その後始末(悪くすれば死体の処理)も、しなければならなかったのである。なお、大勢の観客がいる御前試合などは、小姓ではなく仲間の騎士が合図を出すこともあったようだ。
以下、図の説明に入る。
(A)
まずは、槍を構えて馬で突進します。(剣ではなく、あくまで槍です)
楯を構え、お互いのスピードと体力で勝負する勝負なので、体力が足りないと、ぶつかったとき、跳ね飛ばされて落馬します。もちろん落馬したほうが負けです。勢いよく突っ込むことは、勇気があることとみなされるため、どれだけ勢いよくつっこみ、敵の盾を狙えるかが勝負の分かれ目。
もちろん、乗っている馬も、「特攻」用に鍛えられた軍馬です。普通の馬では、敵に突っ込むときに恐れて逃げてしまいますから。
(B)
…と、いうわけで、「どりゃア!」と、突っ込みました。
このとき、当然ですが互いの勢いが同等だと、槍が折れます。勢いが劣っていたほうは、馬から落ちます。落ちたら負け。両方とも馬に乗ったままだったら、次のステップへ。
(C)
実際の戦場では槍が折れても代わりを調達して何本でも使っていたようですが、試合では原則として一本きり。槍で決着が付かなかったら、馬を降りて接近戦での勝負です。ちなみに、片方の槍が折れ、もう片方の槍が残っていても、槍を持っているほうは、剣の相手に対し槍を使うことは出来ません。剣・徒歩の敵に対し、リーチの長い槍で戦うのは、卑怯とみなされたからです。また、先に馬を下りることは敗北を意味するので、剣で戦うときは相手に呼びかけ、二人同時に馬から下りなければなりません。
互いの力に差があると槍の突進の時点で既に勝負がついてしますのですが、同等であった場合、双方の槍が折れて徒歩での戦いまでもつれこみました。また、相手が落馬したあとも、馬上に残ったほうが敢えて自分から馬を降り、戦いを続行させることもありました。剣による戦いでは、技、スピード、精神力など、総合的な戦いの能力が必要になります。いわゆる見せ場ってやつです。
(D)
剣での戦いは通常、相手を組み伏せて終りです。よほどの憎しみがないと、殺してしまうには至りませんでした。負けたほうが敗北を認め宣言すると、勝敗が決します。負けを認めたくない、と言い張って、「さぁ殺せ」と言う騎士もいますが…。
負けたほうの生死は基本的に勝ったほうにゆだねられ、その場で「恭順の誓い」を得るか、他の代償を得るか、あるいは殺してしまうか、自由に選ぶことが出来ます。
恭順の誓いは、勝ったほうの軍門に下ることを自ら宣言する行為ですから、これを破ることは、騎士の名誉にかけて許されません。
また、他の代償とは、保釈金(身代金)の要求、「自分のかわりに○○を倒してほしい」といった難しいお願いから、「○○王に伝言をヨロシク」などといった簡単なものまで、様々のようです。
身代金は身分の高い人を負かした場合は当然のように高くなり(城ひとつ取ったりする…)、決闘=騎士の収入源 でもありました。
…以上が、騎士文学に見られる、騎士同士の決闘の、基本的なルールである。
・例外/
馬で戦えない場所、どちらかが馬や槍を持っていない、などの場合は、いきなり剣から勝負はじめることがあるが、これは正規の一騎打ちではなく、単なるケンカのようです。
また、決闘には、「人の代理として」行うものもあった。戦いのルールは同じだが、勝利条件や、勝利の目的が異なる。
代表的なものとして、2つ例を挙げてみる。
■代理決闘1―貴婦人に対する恋愛奉仕
| 「かわいい娘よ、と領主は言う、こうしなさい、私が許すから――これは宮廷風の礼儀にかなっているからね――何かお前の愛情の証しの品をあの方に贈りなさい、小袖かショールを」 するととても素直な姫は言った―― 「よろこんでそうするわ、お父様がおっしゃるんですもの。でも、あたしの袖はとても小さいから、とてもあの方には差し上げられない。もしお贈りしても、きっと、なんだ、こんなもの、なんて言われそう」 ―クレティアン・ド・トロワ「ペルスヴァルまたは聖杯の騎士」―ゴーヴァンと小袖姫(天沢退二郎/訳) |
騎士は、貴婦人のために、その代理として戦うこともあったが、その際、「私は貴婦人の代理として、その騎士として戦っています」ということを表すため、盾の裏側に袖や肌着などを打ち付けることがあった。
例に挙げたのは、姉姫と幼い妹姫の間で口げんかになり、ぶたれた妹姫が、旅の途中のゴーヴァンに自分の屈辱を雪ぐため戦って欲しいと頼んでいるシーンだ。姫はまだ幼いため、袖も小さい。妹姫はそのことを恥ずかしがっているのである。
盾は戦いの中でぼろぼろになり、裏に取り付けられた袖やショールも穴だらけになってしまうのだが、騎士は戦いが終わったのち、それを元の持ち主に返さなくてはならない。それは、「私はこの戦いで、あなたのためにこれだけ激しく戦いました」という自慢と、「あなたの愛に守られ、ぶじ、生きて帰ることが出来ました」という報告の役目を果たす。
袖を与えた相手が生きて帰らないこともあり、そんなときは、血に染まった袖を受け取って泣き崩れる貴婦人の姿が描かれる。
騎士文化華やかなりしシュタウフェン朝時代、既に貴婦人の袖をつける風習は廃れていたというが、その時代にあっても、騎士文学中には貴婦人のかたみの品を受け取る古風な主人公たちが生き生きと描かれている。
■代理決闘2―裁判
| 「何ですって?」 と王妃は言う、「わたくしがそなたの弟を、卑劣な仕方で、故意に殺したと言われるのか?」 「そうです」、とマドール、「貴女は弟を、卑劣にも欺いて死なせたのです。もしこの場に、決闘場で貴女のために私と闘おうというほどの騎士が居るならば、今夜か明日、あるいはこの宮廷が取り決める日に、その騎士を殺すか降参させるまで戦う覚悟です」 ―作者不詳「アーサー王の死」―67(天沢退二郎/訳) |
中世騎士社会において、証拠のない裁判は「決闘」で行われることもあった。
神の加護は正しい側にある、従って決闘によって生き残ったほうが正しい、というわけだ。
しかし女性や、なんらかの事情で体の動かせない者は自ら闘って潔白を証明することが出来ない。そこで、代理の騎士をたて、代わりに闘ってもらう。
例のシーンは、13世紀に書かれた作者不詳の「アーサー王の死」より。王妃グニェーヴル(グウィネヴィアのこと)の宴で、ゴーヴァン(ガウェインのこと)を殺すべく仕掛けられた毒りんごを誤って口にしたガエリスが死んでしまう。その兄マドールは王妃がガエリスを毒殺したものと思い込み、決闘による裁判を望む。
結局、王妃の代理としてはランスロ(ランスロットのこと)が立ち、勝利して王妃の潔白は証明される。
…しかし、力で正義を証明するというのは、現代からすると何とも釈然としない。煮えたぎる湯に手を突っ込むとか、火にカメの甲羅をかけるとか、過去、古今東西において不思議な身の潔白の証明は数多く行われてきたわけだが、これも、その一つと言えるかもしれない。